鷹栖ソーシャルワーカー懇話会参加報告
長濱ゼミ専門ゼミナール(3年生)の活動報告です。
皆さん、こんにちは。
コミュニティ福祉学科3年の福原知謹(ふくはらともちか)です。
僕らが所属している長濱ゼミの指導者である長濱先生は、
僕らが目指しているところの【社会福祉】とは何なのかを問いてくることがあります(直接的な問ではありませんが)。
この僕らが養成を受け、得るであろう【社会福祉士】とは、【社会福祉】を担うつまりソーシャルワークに専門性をもって行う職種となります。
IFSW(国際ソーシャルワーカー連盟)及びIASSW(国際ソーシャルワーク学校連盟)が2014年に採択した定義として、
「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理はソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学および地域・住民固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。」
と定義をしています。
つまり、この定義にもあるように、社会の充足と変革に働きかけ、また、社会で足りない部分は開発するために、【学問】として追求しなければならないというわけです。
この【学問】としての追求の為には、大学での研究および発信はもちろんのこと、
様々な社会資源(つまり様々な人や物)と繋がること(【ネットワーク】を構築する)により、社会福祉を充足するための【(a) must】を深めることではないかと僕は自分自身では理解しております(正解がどうかはわかりませんが)。
その社会資源と繋がるための【機会】を大学のうちにどれだけ提供してもらえるのか(その【機会】を大学のうちから継続できるのかはその学生の能力によると思いますが)というのが、コミュニティ福祉学科の全体のゼミの【価値】の一つではないのか、というのが、僕の見解です。
今回は、その【機会】として先生が所属している勉強会(鷹栖ソーシャルワーカー懇話会)に長濱ゼミ3年生として、去る2023年11月18日に参加してきました。
なお、
「鷹栖ソーシャルワーク懇話会」とは、主に鷹栖町に在住のソーシャルワーカー(以下、SW)を中心として、毎月1回開催され現在通算127回(つまり10年間)続いている団体であり、勉強会や事例検討会を行っている団体です。
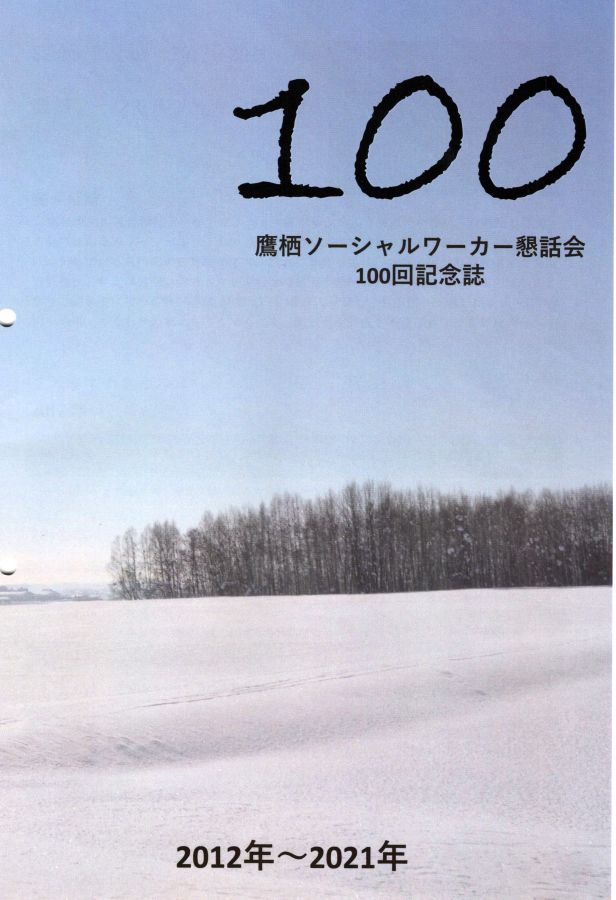
メンバーとしては、
障害者総合支援センターのSW、鷹栖町の行政の福祉課、相談事業所や福祉事業所のSW、社会福祉協議会のSWや包括支援センターのSW、小学校の先生そして長濱先生などがメンバーとしています(総勢30人強)。
ちなみに、私、福原知謹も今年の5月からこの鷹栖ソーシャルワーク懇話会のメンバーとして所属しております(長濱先生に頼んで懇話会に参加させてもらいメンバーに入れて頂きました)。
今回は、僕も参加しました、10/21に鷹栖町および鷹栖ソーシャルワーカー懇話会主催により開催された星槎大学堀越由紀子教授をお迎えして行われた
「鷹栖町地域共生社会フォーラム」
における題目である「虐待はなぜ起こるのか?~津久井やまゆり園事件から学ぶ虐待防止」の振り返りを行いました。
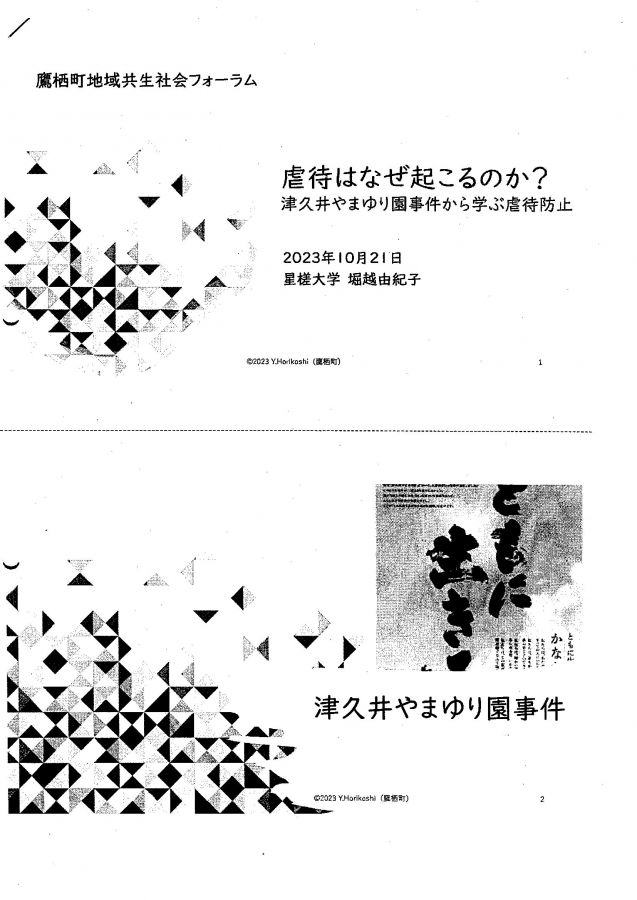
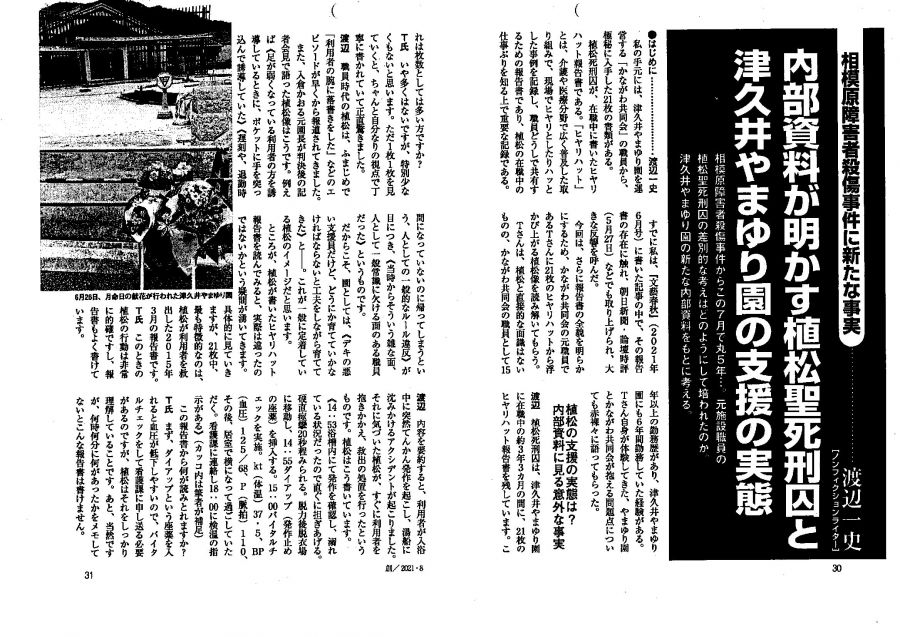
我々長濱ゼミの活動の目的としているところの、
『身体的・知的な部分で何かしらのバリアを抱えている方である当事者とその環境に目を向けその相互作用への分析と考察をし、
よりよい世界を目指す為に学習及び研究をおこなうことを目的とする』を定義している組織としても、
【虐待はなぜ起こるのか??】
を追求することは、よりよい世界を目指す為に必要な【(a) must】であると考えております。

(今回は、ゼミ生の熊谷さんにも参加して頂き、グループワークを行いました。)

(僕と熊谷さんが参加したグループ。同席者は第一線でご活躍されているソーシャルワーカーの面々です)
それでは、今日初参加された熊谷さんの感想です。
熊谷鈴夏
鷹栖ソーシャルワーカー懇話会
私は今回初めて鷹栖ソーシャルワーカー懇話会に参加させていただきました。福祉業界で働いている現役のソーシャルワーカーの方や行政の方などとディスカッションができる貴重な機会をもてることを嬉しく思い、とても勉強になる話し合いができました。
今回の「津久井やまゆり園事件から学ぶ虐待防止」の振り返りにおけるディスカッションを通して、事業所や施設等の福祉領域全体の共通認識として、「外部からの風」が必要ではないかと感じました。それというのも今回のトピックとして虐待のことについて話し合ったためです。虐待についての中でも自分が深く考えたのは、虐待に関する福祉従事者と第3者間での認識の違いについてです。現場においての「虐待」と外部から見る「虐待」とでは、その認識にズレが生じてしまうことが多いのではないかと感じました。
例えば、施設の職員と利用者が遊びでなにかをしていたとします。それを第3者がみて「虐待だ」と認識する前に「もしかしたら遊んでいるのかも」と思えるほどに施設での様子が第3者にとって身近であること、また職員側が「第3者から見ると虐待になるかも」と意識することで、内外部での認識の違いを生むことは防げるのではないでしょうか。
地域と福祉現場の壁をとって、外部からの風を受けるとともに、こちら側もまた風を送り、社会全体で巡らせていくことが必要となっているのではないかと考えます。そのために、地域と現場のつながり・結びつきを深めるための情報発信や交流は重要であるのだと実感として得ることができました。

(まとめの報告をしている熊谷さん)
熊谷さんは次回より正式な会員として鷹栖ソーシャルワーカー懇話会に参加することになりました。
みなさん、これからもよろしくお願いします。
このような会に所属し、グループワークを行う【価値】を一つ考えるならば、
それは、
「学術面での教科書に書かれていない現場の声が聞けること」
なのではないか考えています。
ここで、今回のグループワークで行われたディスカッションを一つご紹介できればと思います。
例えば、今回の「虐待」のことを考えるならば、当然、虐待を行うことは間違っています。
当然、それを理解した上で、例えば施設の方々は業務を行っているはずです。
しかし、この事例を考えた場合どうなるのでしょうか??
「利用者の方が、バスに乗っているときに、感情が高ぶり暴れてしまった。そのとき、運転手は運転しているし、他の利用者の方も乗っている。その時、暴れた利用者が他の人に危害を加えないように、ワーカーが暴れた利用者の手をとり制止した」
この場合、一連の行動を考えた場合、虐待ではありません。
ただ、
「ワーカーが利用者の手をとった」
このシーンだけを目撃した第三者にとっては、「虐待」と捉えかねない可能性は大いにあるということになります。
当然、この時の目先の解決策としては、
「誤解されないように注意しなければならない」ということになるとは思います。
ただ、これは正解なのでしょうか??
僕は、これはただの【応急処置にすぎない】としか思えないのです。
僕ら【社会福祉】を学んでいる人間は、福祉としての【応急処置】を追求するところにないということをこのような会で再確認することができます。
つまり、先程の事例でいうならば、
「利用者が感情を高ぶらせてしまったり、
暴れたり、そうならない為に、その人にとってどうしたらよかったのか」
ここを追求することが大事なこととなります。
最後に、今回の振り返りを含めて毎回の懇話会で学ぶことは以下のことにつきると僕はいつも思っています。
社会福祉を学び、追求する人間にとって、
「私達は何の為に存在するのか」
そこを追求することであり、それは、アドボカシー(権利擁護)であり、オンブズマンとして学びを深めることであると考えます。
そしてその学びを発信し続けることが、僕らの責務であると感じております。
旭川市立大学
コミュニティ福祉学科3年
福原知謹

